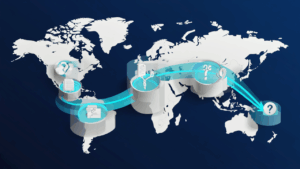日本の漫画は、本当に“世界一”か? 元・米国法人COOが語る、ウェブトゥーンとアメコミから学ぶべき3つの「生存戦略」
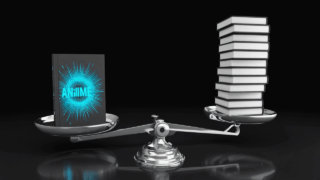
『ONE PIECE』、『呪術廻戦』、『【推しの子】』…日本の漫画が、国境を越えて世界中の人々を熱狂させているのは、紛れもない事実です。その卓越した作画技術、読者を引き込むストーリーテリングの力は、世界に誇るべき日本の文化資産です。
しかし、その輝かしい栄光の影で、静かに、しかし急速に地殻変動が起きていることにお気づきでしょうか。
韓国発の「ウェブトゥーン」が、スマホネイティブ世代の時間を席巻し、アメリカのコミック市場では、スーパーヒーローだけではない、驚くほど多様なテーマの作品が次々と生まれています。
初めまして。グロース戦略パートナーのJapanConnectAdvisoryです。 私はかつて、ある大手電子書籍プラットフォームの米国法人COOとして、日本の漫画を世界に届ける最前線にいました。そしてそれは同時に、日々勢いを増す海外の競合たちの戦略と、すぐ隣で対峙する日々でもありました。
これは単なる海外事情の解説ではありません。日本の漫画が、この変化の激しい世界市場で10年後、20年後も“王者”として勝ち続けるための*実践的な「生存戦略」です。
戦略1:『IP創出エンジン』を回せ – ウェブトゥーンのビジネスモデルから学ぶ
ウェブトゥーンのビジネスモデルを分析すると、彼らが漫画単体で大きな利益を上げる「薄利多売」の構造であることが見えてきます。「待てば無料」を基本とし、多くのユーザーは無料で楽しみ、一部の熱心なファンが「先読み」のために少額課金する。しかし、それは壮大な戦略の序章に過ぎません。
彼らの真の狙いは、ウェブトゥーンプラットフォームを巨大な『IP創出エンジン』として機能させることにあります。
プラットフォーム上で毎週、数え切れないほどの新作が公開され、読者の閲覧データ、コメント、評価といった膨大なフィードバックがリアルタイムで蓄積されます。このデータに基づき、「どの作品にヒットの可能性があるか」を極めて高い精度で予測し、選別されたIPは、即座にクロスメディア展開の企画へと回されるのです。
【具体的な成功事例】
- 『俺だけレベルアップな件』: カカオピッコマで143億回以上閲覧されたウェブトゥーンは、A-1 Pictures制作でアニメ化され、世界中の配信プラットフォームで大ヒットを記録しました。
- Netflixとの連携: 『梨泰院クラス』『Sweet Home -俺と世界の絶望-』『今、私たちの学校は…』など、数多くのウェブトゥーン原作ドラマが制作され、Netflixのグローバルランキングで1位を獲得。原作の閲覧数も、映像化をきっかけに爆発的に増加するという相乗効果を生んでいます。
NAVERウェブトゥーンは、このIPビジネスを収益の重要な柱としており、2023年には年間約1.3億ドル(約200億円)もの売上を上げています。ウェブトゥーン市場全体も凄まじい勢いで成長しており、2023年に約82億ドルだった市場規模は、2030年には450億ドルを超えると予測されています。
彼らは漫画を売っているのではありません。データに基づいてヒットの種を見つけ出し、低リスクで映像化・ゲーム化などに繋げる、極めて効率的な『IPインキュベーション・プラットフォーム』を運営しているのです。このスピードとシステムこそ、我々が学ぶべき最大のポイントです。
戦略2:『設計図』としての原作を創れ – 米国コミック市場から学ぶ
アメコミもまた、原作単体で見れば「薄利多売」の構造です。北米のコミックブック市場の年間売上は、全体で約20億ドル規模。これ自体も大きな市場ですが、彼らがIPから生み出す価値は、その比ではありません。
【衝撃的な数字の対比】
- 北米コミック市場(年間):約20億ドル
- MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の映画興行収入(累計):300億ドル以上
この桁違いの数字が示す通り、彼らにとってコミックブックとは、壮大なクロスメディア展開の、ほんの入口に過ぎないのです。コミックは、熱心なコアファンに向けて世界観やキャラクターの魅力を提示し、市場の反応を見るための「実験場」であり、巨大なビジネスを生み出すための「設計図」なのです。
【具体的な成功事例】
- マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU): 2008年の『アイアンマン』から始まったこのプロジェクトは、個々の作品が伏線を張り合い、時にクロスオーバーすることで、単体作品では成し得ない巨大な経済圏と熱狂的なファンコミュニティを創出しました。
- 『The Walking Dead』: 元々はインディーズの白黒コミックでしたが、AMCでのドラマシリーズが記録的な大ヒット。その後、数々のスピンオフドラマ、ゲーム、グッズなどが展開され、IP全体で100億ドル以上の経済効果を生んだとされています。
彼らは、コミックという「原作権」を源泉に、映画、ドラマ、ゲーム、マーチャンダイジングという巨大な収益ピラミッドを築き上げています。日本の漫画も、「単行本の売上」をゴールとするのではなく、その先の壮大なクロスメディア展開を見据えた「設計図」として、IPを企画・創造するという視点を持つことが不可欠です。
戦略3:『作家』に全てを託すな、『データ』と共に創れ – スタジオ方式から学ぶ
韓国のウェブトゥーン業界で主流となりつつあるのが、複数のクリエイター(脚本家、作画担当、着彩担当など)が分業し、データ分析に基づいて読者の反応をリアルタイムで見ながら高速でPDCAを回す「スタジオ方式」です。
もちろん、これは日本の伝統である、一人の天才的な「作家」の才能と情熱が生み出す奇跡を否定するものでは全くありません。しかし、その属人的なモデルには、ヒットの再現性が低く、作家個人への負担が極めて大きいという構造的な課題も存在します。
私がサントリーでDX推進をしていた時の最大のテーマは、「勘と経験の経営」から「データドリブンな経営」への転換でした。これは漫画作りにおいても、極めて重要な視点です。
- 「この展開は、海外読者の離脱率が高い」
- 「このキャラクターの登場シーンは、エンゲージメントが特に高い」
- 「A国ではBというテーマが、C国ではDというテーマが響きやすい」
こうした客観的なデータを、作家や編集者が新たな「武器」として活用する。作家の才能と、データの羅針盤を組み合わせた「ハイブリッド型の制作体制」を構築すること。それこそが、グローバル市場でのヒットの確率を飛躍的に高めるのです。
日本の漫画の「魂」を、未来へ
日本の漫画が持つ魂、物語の力は、今も昔も世界最高だと私は信じています。 しかし、その魂を乗せて運ぶ「船」の設計や、進むべき針路を示す「航海術」は、残念ながら旧式のまま、世界の潮流から遅れ始めているのもまた事実です。
世界の競合から謙虚に学び、彼らの強みを我々の強みと融合させる。それこそが、この荒波の絶えない世界市場で、日本の漫画がこれからも王者として君臨し続けるための、唯一の道です。
貴社のIPポートフォリオと、グローバル市場における競合の動向を客観的に分析し、次の一手を共に考える【グロース戦略診断レポート】から、未来への航海を始めてみませんか。
ご連絡を、心よりお待ちしております